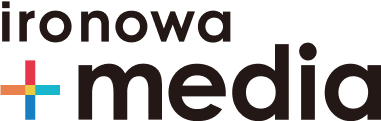大塚に響くわっしょい!御神輿初担ぎ体験記

夏といえば、やっぱり神輿の季節。9月13日と14日、豊島区大塚の江戸橋町会で、神輿渡御が行われました。「神輿渡御(みこしとぎょ)」とは、神社の祭礼で神輿を担ぎ、神様を町中にお連れする大切な行事のこと。威勢のいい掛け声とともに、まち全体がひとつに染まります。
そんな中、「担いでみる?」という嬉しいお声がけをいただき、「これはチャンス」と筆者も思い切って参加することに。初挑戦の肩は早々に悲鳴を上げましたが、心の中は熱気と笑顔でいっぱい。
気さくに迎え入れてくださった江戸橋町会の皆さんに感謝しつつ、ほっこりと熱い御神輿デビュー体験をお届けします。
| この記事を書いた人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 大嶺晋弥 大嶺晋弥 |
周りがヨイショしてくれるとついワッショイしちゃう人。担ぐのも担がれるのも好きなタイプ。 |
||||||
御神輿はなぜ担ぐのか
神様を地域に迎えるための「乗り物」

御神輿は神様専用のタクシー……いや、タクシーじゃ軽すぎますね。神様をお連れする「超重量級の乗り物」です。祭礼のとき、神様は神社から御神輿へ移り、町を巡ります。その意味は、五穀豊穣や無病息災を願い、人々の暮らしを守ってもらうことにあります。
神様とドライブ!

担ぎ手はただの力仕事ではなく、神様を背負いながら地域を共に歩む大役を担っています。快適な最新モデルのテスラよりも歴史と想いが詰まったヴィンテージ木製神輿の方が、神様はお好きなのかもしれません。
神輿装束と一体感
法被に足袋、祭り人の正装

祭りの服装は地域ごとに微妙に違いますが、基本は法被、腹掛け、股引き、足袋。動きやすさと統一感を兼ね備えています。「締め込み」というふんどしの一種で、ほぼお尻が出る大胆なスタイルで神輿を担ぐ強者もいます。言わば祭り版クールビズです。
初参加の筆者は「サンダルで行ける?」と危うく無礼を働くところでしたが、知人に足袋を借りてギリギリセーフ。足袋って、地面を掴んで踏ん張りが効くんです。これがなければ坂道で転がっていたかもしれません。
同じ装いで「仲間」になる

衣装を揃えると、自然と「俺たち仲間だ」という一体感が生まれます。背中に刻まれた町名を背負うことで、不思議と背筋がピンと伸びるのです。見た目も気分も、しっかり神輿モードになれました。
掛け声と下町の絆
「わっしょい」に込められた意味

神輿の掛け声は地域で違いますが、多くの人がイメージするのはおそらく「わっしょい」という掛け声かと思います。この言葉には「和を背負う」「みんなで一緒に担ぐ」という意味があるとか。声を合わせるだけで疲れが吹き飛び、不思議と足が前に出ます。
町内会に流れる温かい空気

神輿を担ぎながらふと周りを見ると、町内会の人々が笑顔で談笑している姿が。子供の頃から顔なじみの仲間が、今は親になって子供を連れてきている。小さな子どもを町全体で見守る姿に、下町らしい優しさを感じました。
難所と宮入のクライマックス
地獄坂を一気に駆け上がる

神輿ルートの最大の難所は「地獄坂」。見るからに急勾配で「ここ無理でしょ…」と心が折れそうになります。ですがベテラン担ぎ手たちは涼しい顔で突破。気がつけば筆者は側道で、掛け声だけを張り上げて応援にまわっていました。
天祖神社での宮入、祭りの頂点

最後は大塚駅近くの天祖神社で「宮入」。江戸橋をはじめ五町会の神輿が集まる姿は圧巻です。境内に戻る瞬間、まるで神様が本殿へ帰っていくような荘厳な雰囲気に包まれます。神輿が降り立つ光景は鳥肌モノ。
神輿渡御を終えたあとには、不思議な達成感が心いっぱいに広がりました。肩を並べて汗を流した仲間たちと酌み交わすお酒の美味しさは、間違いなく人生トップクラスです。豊島区・江戸橋の神輿は、まちの心をひとつにするかけがえのないものでした。
その熱気と一体感は、まさにまちの魂そのものです。ただ近年は、担ぎ手の数が少しずつ減っているそう。もし機会があれば、皆さんもぜひ参加してみてください。汗と笑顔に包まれたあの時間は、きっと一生忘れられない宝物になります。