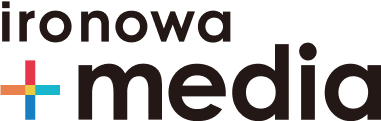灯と太鼓が揺らす秋夜!鬼子母神御会式

秋風が少し冷たく感じる頃、雑司が谷の夜がいっそう華やぐ3日間があります。江戸の面影を今に残す「鬼子母神御会式(おえしき)」。地域の人々が何百年も受け継いできた光と音の祭りの魅力を、実際に足を運んで感じたままに伝えたくなりました。
| この記事を書いた人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 大嶺晋弥 大嶺晋弥 |
屋台の灯を見つけると虫のごとく引き寄せられる。気づけば焼きそば片手に、万灯(まんどう)の光を追っていました。 |
||||||
灯と太鼓が織りなす秋の夜
江戸から続く「ありがとう」の祭り

御会式(おえしき)は、日蓮聖人の命日に感謝を捧げる法会が始まり。しかし、雑司が谷では宗派を超え、誰でも参加できる「街ぐるみの大祭」へと発展しました。「宗教だから」ではなく「面白そうだから」という気持ちが原点。その自由で温かい空気こそ、雑司が谷らしさなのです。
まるで和のエレクトリカルパレード

夜7時を過ぎると、街の灯りが一変します。真っ白な紙花に包まれた「万灯(まんどう)」が、ゆらゆらと光を放ちながら練り歩く。太鼓と団扇太鼓(うちわだいこ)のリズムが街を包み、まるで和風エレクトリカルパレードのよう。その幻想的な光景に、思わず足を止める人が後を絶ちません。
万灯・纏・太鼓――三拍子そろった迫力
勇ましくも優しい「纏(まとい)」の舞

行列の先頭で揺れるのは、先端に飾りをつけた長い棒「纏」。もともとは江戸の火消しが、自分たちの組を示すために振っていたもの。「纏を振る姿は、街を守る心の象徴でもある」と話す地元の方の言葉に江戸っ子の粋を感じます。
白い花咲く「万灯」の華やかさ

高さ3〜4メートルもの万灯は、白い紙花を500枚も使ったという力作。夜空に咲く巨大な枝垂れ桜のようで、光に照らされると息をのむ美しさです。平成27年には豊島区の無形民俗文化財にも指定。受け継がれてきた技と想いが、風に揺れる花びらの一枚一枚に宿っています。
街がひとつになる夜
17日・目白台から 18日・池袋から

御会式のクライマックスは、17日の清土鬼子母神からの行列、そして18日、池袋駅前から出発する「万灯練供養」。明治通りを練り歩く光の列に、外国人観光客もカメラを構えます。池袋の喧騒に太鼓が響き、普段とは違う街の表情に思わず見入ってしまいます。
屋台と笑顔、そして懐かしさ

参道にはずらりと並ぶ屋台。焼きそば、りんご飴、綿菓子に金魚すくい。鬼子母神堂の境内には創業1781年の老舗駄菓子屋「上川口屋」も健在。屋台から漂う美味しそうな匂いに誘われ、つい財布の紐がゆるみます。子どもも大人も笑顔で行き交う光景に、地域の絆を感じました。
鬼子母神堂に込められた祈り
「鬼」にツノがない理由

「鬼子母神」と書いても、実は“鬼”にツノがないのです。かつて子どもを食べていた鬼女が、日蓮聖人の教えで改心し、子どもを守る神様になったという伝説がもと。その優しい表情の像に、安産・子育ての願いを込めて参拝する人が絶えません。
変わらぬ祈り、変わりゆく街で

江戸時代から続くこの祭りが、令和のいまも変わらず受け継がれているのは、地域の人々が心でつながっているから。スマホの光よりも、手作りの万灯の明かりが温かく感じる夜。この光が、雑司が谷の未来を優しく照らしてくれる気がします。
太鼓の響きと万灯の光が、秋の夜を彩る御会式。宗派も世代も越えて、人と人が笑顔でつながる。雑司が谷の夜は、今年もやさしく、あたたかく輝いていました。